自然界の植物から学ぶことって本当に多いと思うんです

自然界を見てみると様々学ぶことが多くあります
その一つが植物です
株式会社 日向の鳥辺康則です(^◇^)

コロナ禍で我々を取り巻く生活環境は目まぐるしく変化していってます
変化に対応する能力を私は植物から学ぶことができると思ってます
自分の生活環境が変化した場合、動物は動くことができるので自らが環境を変えたり、移動したりすることができます
しかし・・・植物は動くことができないのです
環境を選べない植物は自らのあり方を合理的に変化させて生き残っているのです

植物の基本的な生き方は・・・
「変えられないものを受け入れる!」
自らが生える環境は代えられません
環境条件は、植物自身は変える力を持たないのです
そして周りに生えている植物も変えることができません
変えられないものは、受け入れるしかない状態の中でできることを精一杯やっているのです
それは「変えられるものは変える!」です

植物は変化に対応するために自分の体や成長の仕方をいかようにも変化させます
環境を変えられないのであれば自らを変化させて生き残っていってるのです
ちょっと専門的な言葉を使うと生物の変化できる能力を「可塑性」といいます
動くことのできない植物は、動物に比べて可塑性が大きいと言われています
先月行った北海道の阿寒湖でもそんな風景をたくさん見れました

植物は根を張り下から上育つものだと私は思っていました
ところが周りにライバルの多い植物は、いち早く光を求めて上に成長するのではなく、光の方向へ成長することもわかりました
周りの植物よりも早く大きくならないと光が当たらないので競い合いながら変化に対応してることがわかりました
そして一番背の高くなった植物だけが生き残るのです

そんな中で自然界で一番学びになるのは・・・
雑草です(笑)
どんな悪環境の中でも生き残ろうと可塑性を最大限発揮します

ライバルがあまりいない土地では茎を横に伸ばしてテリトリーを広げていきます
しかし一旦ライバルが現れると、競争力を高めるために横ではなく上に成長し始めるのです
ビジネスと言うのであれば、大きな変化が現れたときに次のようなことが言えます
・新たな業種やテリトリーへ拡大するべきなのか?
・今あるビジネスや顧客を強化するべきなのか?
どちらの戦略が有利なのかと考える事は実を言うと馬鹿げています
なぜならばその時の状況によって変わるからです
雑草は臨機応変に瞬間瞬間にその時の状況によって変化し続けています

さらに雑草はこの2つ以外にも、変化に対応するべきありえない成長の仕方をすることが多くあります
植物図鑑を見てもその事は書いてありません
つまり私たちが考えている通りの成長をしないと言うことです
われわれは常に固定観念の中でしか変化に対応しませんが、雑草は固定概念を超えて自由自在に変化し続けます
これってすごいと思いませんか?

人間は動植物の中で最も変化を嫌い、可塑性のない生き物だと言われています
人間の変化への対応の仕方は、相反する2つの考えがベースとなっているみたいです
一つは、「変化に惑わされず、1つのことに専念して継続することが大事!」と言う考え
もう一つは、「同じことを続けていてはいけないと思い、変化に対応して順応性を持って行うこと!」
どちらもとても大切なことだと思うのですが、例えば企業理念や目的や動機は、どんなに周りの環境が変わろうとも創業の思いや土台になってる部分なので変えるべきではないと思っています

植物で言うと根を張った幹の部分です
しかし枝葉の部分は周りの環境によって変化に対応して変えるべきだと思っています
固定概念に縛られず、どんどん変化し続けることのみが生き続けることだと思っています
やってみてダメだったらどんどんチェンジして変化させ続けたらいいのです
環境が大きく変わっているのに何もしないことが1番の失敗だと思っています
そして絶対にやらない後悔よりも、何かにチャレンジした後悔の方が良いと思っています

自然界の動植物はすべて環境の変化とともに可塑性を持っているにもかかわらず、人間だけが拒んでいるような気がします
日頃みんなが気にしない雑草1つでも学ぶことができるのです
日々が学びであり、感謝であると思っています
われわれは自然の1部であり、自然界から学ぶ事はまだまだ多くあります
そんなことを雑草を見て感じたのでブログに書きました(^◇^)

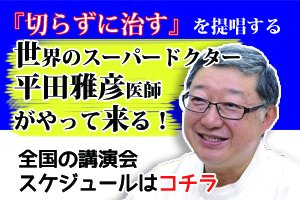















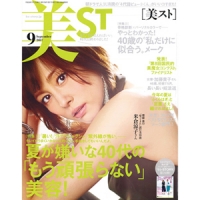

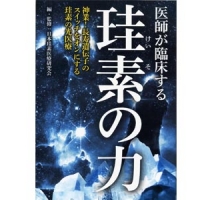



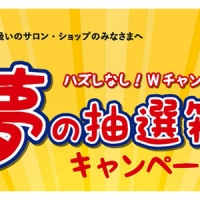

No comments yet.